kintoneおじさんの会に参加してみた!
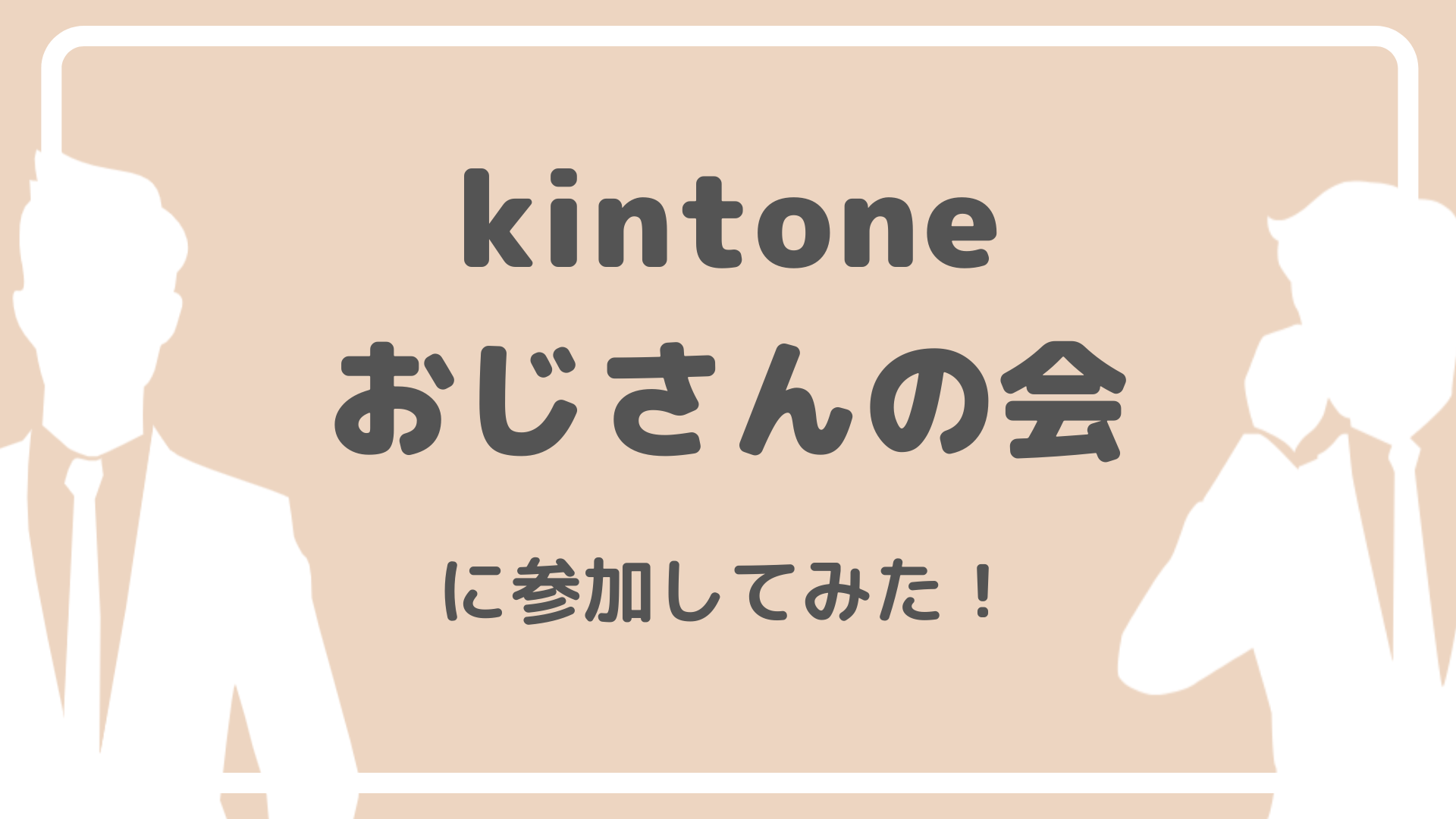
今回は3/4開催の「kintoneおじさんの会」に潜入!
試しに覗いてみると、これが非常に実践的なkintone雑談の会だったんです。kintoneに関わる様々な立場の方が集まり、活発な意見交換がされていました^^*
配信アーカイブが公開済みなので、ぜひ見ていただきたいです!ただ、2時間のボリュームなので、中々最初はハードルもあると思います。
ということで、私の印象に残ったフレーズをピックアップしていきます。ぜひこちらを参考に、アーカイブを視聴してみてください!
配信アーカイブ
当日のYouTube Liveは、既にアーカイブが公開されています。YouTubeは倍速再生もできるので、速度調整しながら聞くのもオススメですよ♪
https://www.youtube.com/watch?v=Ahi9veXtnpwkintoneおじさんの会とは?
そもそものキッカケはTwitter。
kintoneおじさんこと安藤さんの業務フローに関するツイートがきっかけでした。「専門職の方はどう学んだのか?」と清水さんも続いていきます。
ムッチャ聞きたかった。
— 安藤 満秋 | kintone おじさん。 (@imarobot_99) February 28, 2020
私たちに必要な事、これな気がする! https://t.co/teluCOdaoE
そこに専門職である飯塚さんのアドバイスも加わり、いよいよ本格的な議論に!これを見ていた松田さんが発起人となり、「kintoneおじさんの会」の開催が決定したのでした。
当日は、kintone開発のプロ 久米さんや、キンスキラジオにも出演頂いたなかじさん、kintoneお姉さんこと士業の星名さんも参加!
プロ/ユーザーの垣根を越えて様々な人が集まり、多角的に意見交換できる素敵な会だったと思います^^*
それでは印象に残った部分をピックアップしていきます!
ピックアップ!
業務フロー・DB設計をどう学び、他の人に教えましたか?
(04:59〜)
ユーザーの清水さんはACCESSを触った経験があり、その経験がkintoneの構築に生きたそうです。
これから他のチームメンバーにも教えていきたく、他の人の経験が知りたいというお話でした。プログラミンの講師も務めている 久米さんが、自分の経験から紹介しています。
1人だと学び方が分からないが、学ばないと大規模開発ができないジレンマ
(11:15〜)
元々1人でkintoneを担当してきた経験から、学びのジレンマを投げかける清水さん。一方で、20年前とは学ぶ環境も、世の中の常識も変わってきているようです。
僕たちは家具は作れるけれど、家は作れない
(17:34〜)
kintoneで作るアプリが家・家具に例えられました。
家具は見様見真似で作れるが、大規模な家になると作れないと悩む清水さん。しかし、久米さんは「家を作らなくても良いのでは?」と投げかけます。
「家を作ることでどんな幸せを掴みたいかが大事」と、より本質にフォーカスすることを語りました。
家を見ないで家具を作っていると、業務側は感じる
(19:43〜)
一方で星名さんは、部分最適でアプリ作成していないか、とユーザー視点の不安を語ります。
全体を見据えながら、アプリを作る必要があるのではないかと。しかし松田さんは、そもそもkintoneと従来のシステム開発は、大きく異なると言います。
kintoneに合った学び方・考え方をプロから吸収する必要があるのかもしれません。
専門職の方が、ユーザーサイドの意見を聞くメリットは?
(26:20〜)
清水さんからは、プロと交流できるのは嬉しいが、逆に現場と交流にメリットはあるのか、と質問が挙がります。それに対して、飯塚さんはkintoneはレアなコミュニティだと答えます。現場の生の声を得られるのは、プロの立場からも貴重な機会のようです。
また、久米さんは現場との会話を「濃縮果汁」に例え、濃い知見が得られていると語っていました。このようなプロと現場が交流できるコミュニティは、世の中を見ても貴重な場なのかもしれません。
何を学ぶ?どう学ぶ?
(33:03〜)
kintoneのコミュニティの発展により、最近は「ひとりぼっち」が減ってきた。一方で松田さんは、「何をどう学ぶか?」という姿勢が重要になっているのではと投げかけます。
また、久米さんからは「データを構造的に捉える」ことの有効性が紹介されます。
ドロップダウンでやるのか、ルックアップでやるのか
(39:15〜)
データ構造を捉える例として、ドロップダウンとルックアップの使い分けが語られました。DB設計の基本で言えばルックアップでマスタ構造を作るべきです。
しかし、kintoneならばシーンによってドロップダウンを選んでも良いと盛り上がります。その中で久米さんからは、kintoneのコツとして「変えられる構造にしておく」が紹介されました。
kintoneは、変えてもいい、間違っていても良いと語られます。
後々破綻するニオイがした時に、そっと道をエスコートしたい
(46:48〜)
kintoneを使うメンバーを増やしたい安藤さんは、正しく導くには知識が必要なのではと問います。久米さんからは「データを一方向に伸ばす」DBの基本的な考え方が紹介されます。
DBを綺麗に設計してきた人にとって、kintoneは気持ち悪い
(57:10)
入力しやすさと、見やすさを両立する必要があるkintone。それは従来の開発に慣れた身としては気持ち悪かったと語る飯塚さん。
一方で、最近はkrewDataも出たことで、入力しやすさに集中することも可能になったと言います。
続きは動画へ!
以上、半分のまとめです
本当は2時間分をまとめるつもりでしたが、名言が多すぎました。まさか半分でこれだけの長さになるとは...(笑)
でも、これだけでも十分に内容の魅力が伝わるかと思います。ぜひ続きは実際の動画を見てみてくださいね!
https://www.youtube.com/watch?v=Ahi9veXtnpw
