#37:標準機能だけじゃ、もったいない! ゆうの森 前島さんと考えるkintone連携サービス
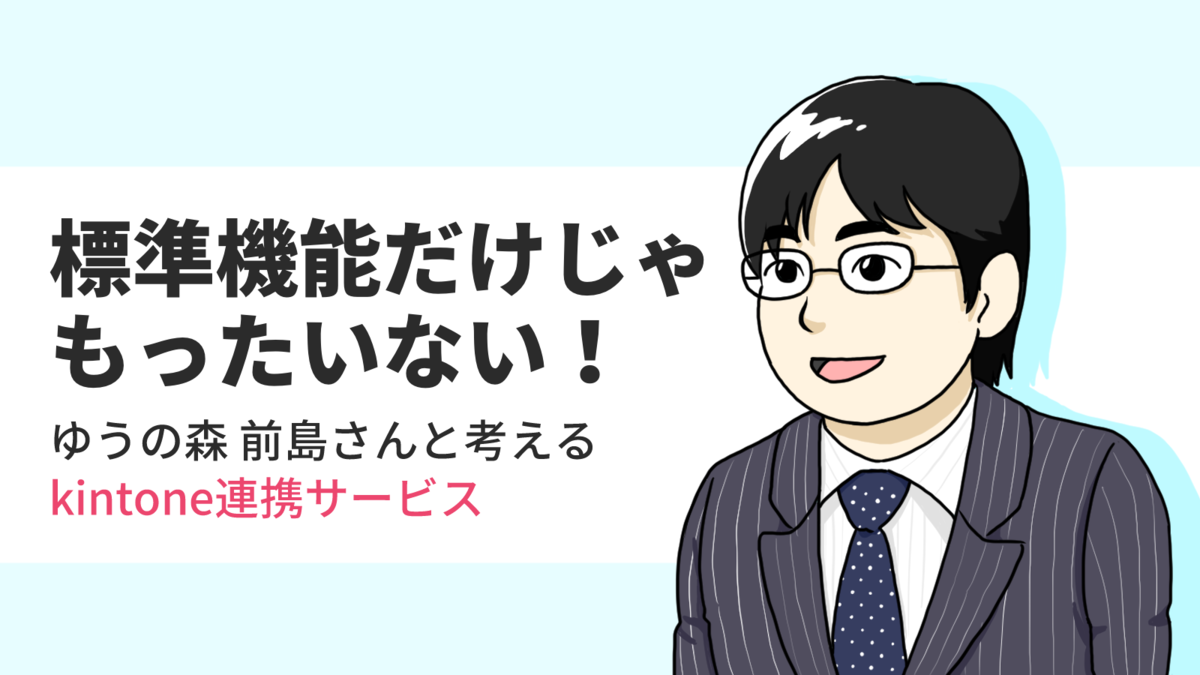
kintone大好きなユーザーさんとキントーク!
今回のゲストは事例掲載もしているゆうの森 前島さん。 地域包括医療の中で活用いただいてるユーザーさんです。
前島さんには、kintoneの標準機能と連携サービスの考え方を聞いていきます。 今までは標準機能を中心にアプリを作っていましたが、 最近は連携サービスを積極的に使う考え方に変わってきたそうです。
その背景をお聞きして行きます。
配信先
キンスキラジオは各メディアで配信をしています。
Apple podcasts(iPhone・iPad)
Google ポッドキャスト(Android)
spotify
YouTube
全文書き起こし
ゆうの森 前島さんについて
(00:00〜)
松井:皆さんこんにちはkintone大好き松井です。今日のキンスラジオではkintoneのユーザー様にお越しいただきました。今回は、ゆうの森の前島さんにお越しいただきました。前島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
前島:前島です。よろしくお願いいたします。
松井:前島さんは明日kintone hive松山がありまして、そちらにもご登壇を頂くことになっているんですけれども、そちらとかぶる部分もありながらかもしれませんが、kintoneのユーザーが必須のスキルというか、そういったところを以前カフェでお話しいただいたのでお聞きしていこうと思うんですが、まずは前島さん、ゆうの森をご存じない方もいるかと思いますので、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
前島:私ども医療法人ゆうの森は、愛媛県の松山市、それから西予市という所にそれぞれ1つずつ診療所を構えていまして、主に在宅医療と地域に根ざした医療というのをやっています。
在宅医療というのは、寝たきりの方とか重い病気でなかなか通院が出来ない方に対して、お医者さんや看護師さんたちが家に来てくれて診察やケアをしてくれるというもので、その方の人生の最期、お看取りのところまでしっかりと住み慣れた家で安心して過ごしていただけるように、24時間対応でお手伝いをさせていただいています。
それから、地域に根ざした医療というのが人口5,100人ぐらいの西予市明浜町というところの地域に1つだけの診療所が以前閉鎖するという話があったのでこちらで運営を引き継いで、うちがやってきた在宅医療を取り入れながら地域の方たちが安心して住み慣れた町、住み慣れた家で過ごしていただけるようにサポートをさせていただいております。
私は、その中で総務系の担当として職場環境の整備とか、書類の手続きだったりとか、IT関係のソフトウェアとか、機器とかでkintoneの管理を担当させていただいています。
松井:前島さんは、kintoneの認定資格もお取りいただいていて、アプリデザインスペシャリストもお取りいただいてますよね。カフェの方でお聞きしていた時もkintoneがお好きでいただいてるんだなと。
前島:はい、私も大好きです(笑)
松井:ゆうの森さんというと、弊社の中の事例でも地域の医療、地域包括医療の1つのパターンとして挙げさせてていただいて、国の方からも活用事例が表彰されたと伺っているんですけれども、意外だったのがてっきり前島さんはシステム系の道を歩んできた方なのかなと思っていたんですけれども、そうじゃないんですよね。
前島:むしろ全く逆で大学も文系だったし、前職は証券会社の営業マンを3年ぐらいやっていたと。
松井:これをお聞きの方、よろしければネットで「kintone ゆうの森」とお調べいただいて、事例のページを見て頂きたいと思うんですけれども、システム担当のバリバリの方なのかなと思ってしまう写真だったんですけど、今日お話していて1番意外なところでした。
前島:事例の動画とか写真を見ていつも言われるのが、システムエンジニアか情シスの人だと思ってたというのと、当時今より痩せていたので違う人かと思ったとかっていうのはあったりします。
松井:そこまで変わらないですよ(笑)
なるべく標準機能で完結
(04:24〜)
松井:そういったイメージもあってかもしれないですし、医療の現場というかITに慣れない方もいらっしゃるかもしれないと思いますが、kintoneの開発とかのカスタマイズもかなり加えているのかなと思っていたんですが、そんなことはないんですよね。
前島:JavaScriptのカスタマイズとか入れてるのはほとんどなくて、アプリも1つぐらいですね。なるべく標準機能で作りながら、時に条件書式のプラグインだったりとか多少見栄えを良くして使いやすくするものを入れたりするんですけれども、なるべく標準機能でできるようにしています。
松井:今日主に聞いていきたいなと思っていたところは、その標準機能と連携サービスとか開発、kintoneのスタンダードコースのところをどう考えたらいいのかといったところをお聞きしたいなと思ってまして。
前島:ええ。
松井:というのも、4月kintoneカフェ松山がありましたけれども、そちらに前島さんご登壇いただいたと思いますけど、その時のタイトルがこれから「kintoneユーザーの必須スキル」というようなテーマだったと思うんですね。
結論で言えば、今求められているスキルは開発じゃない方においてもkintoneの標準機能に加えて連携サービスとか、CUSTOMINE、このあたりで知識を身につけておいた方がいいよと、自分たちでできることが広がっているからだよと、そういったことをお話いただいたと思うんですね。
前島:ええ。
積極的に開発していた時期
(06:29〜)
松井:この辺りをゆうの森さんの事例と照らし合わせながらお聞きしていきたいなと思っているんですけれども、先ほど出来る限りkintoneの開発だったり追加のところを加えないようにされているというお話はあったんですけれども、それは1番最初から思われていたんですか。
前島:いえ、導入して少しした頃に色を変えてほしいとか、強調してほしいとか、Googleマップとかと連携できたらいいんじゃないかという話はあったりして、私もプログラミングできないんですけれどもdeveloper networkのサイトなんかを見てサンプルプログラムをコピペして取り入れたりしてみたりして、すごいでしょっていう感じで仲間に見せたりしてたんですけれども。
松井:結構楽しいですよね。可能性が広がるし、開発者の気分になって動いたというか。
前島:自分がスキルアップしてるような感覚もあったりしてたんですけれども、当時は5年ぐらい前ですからプラグインが出始めたところで、まだまだプラスアルファの開発というのはJavaScriptとかでガリガリ書いてやるという選択肢が。
松井:2013年ですよね。プラグインが出た年ですかね。選択肢もなかった中だと、developer networkが開き始めたぐらいでしたかね。サンプルなんかがあってですよね。それを試してみて皆さんからも色が変わったとか地図が出た。それを止めようというか、良くないなと思ったのは。
前島:そうやってやってた時に見た目とかも良くなってるし、達成感もそれなりにあるんですけれども、それをしすぎるとkintoneらしいいつでも変更できますというのがないなと、違うかなと思い始めていたんですね。
松井:なるほど。
青竹のふし 青山さんとの出会い
(09:14〜)
前島:そう思い始めていた時にふと出会いがあって、青竹のふしの青山さん。本当に素晴らしい事例でサイボウズさん経由で引き合わせていただいて、近い業界の活用だったりしたのでフォーカスしてもらった時に次元が違っていたというか。
kintoneのできないところをプラスアルファしてカスタマイズするという次元じゃなくて、kintoneはそもそも社内で使うものとその時は完全に思っていたんですけれども、そうでなくてお客様である利用者さんがユーザーになってて、その中で報告をしたり、意見交換をしたり、請求書もkintoneの中で見れますみたいな。
そうした時に自分たちってまだまだ、社内でkintoneは使っているけれど患者さんには電話だったり、地域の病院とかケアマネージャーさんにはファックスで報告をしてるとかってまだまだアナログだったので、kintoneでしかもほとんど標準機能でここまでできるんだと。
kintoneのこの機能をどう使うかっていうよりは、ツールをどう取り入れていけばこの仕事がなくなる、例えば電話をしなくてよくなるとか、お客さんにとっても情報がどうやったら見やすいかとか。
そういう1個上のレベルの話だったので自分の中では衝撃を受けたし、その時にカスタマイズとかっていうことでなくて、kintoneをどう作り変えるかじゃなくて、何のために使うかみたいなことが大事だなと思い始めて。
松井:なるほど。
前島:まずは手元の業務とか仕事とかがエクセルとかになってるんですけれども、そういったエクセルがそもそもいるのかっていう所からしっかり考えながら。標準機能でできることをなるべくやっていって、ってなってからは、標準機能でやってて十分大抵の仕事はいけてるかなと思うし、逆に出来すぎると全部kintoneでやっちゃうんですけど、ちょっと標準機能でできないことがあるほうがそもそもこの仕事いるのっていう問いも生まれやすいかなと思ったり。最近になって振り返ってみるとそうだったかなっていう話なんですけど。
松井:今のどうやるかっていうよりは何のためにっていうところですよね。ラジオで他の方の話を聞いていても、特に開発者目線の話ですね、kintoneのできないことがあるおかげで本質の業務に目が向けられる。なんでもできちゃうとみんな欲が出て、ここで色変えて欲しいとか、もっと見た目こうして欲しいとか。
前島:そうなんですよね。
松井:地図が欲しいとか。本質的にそれって改善するためにいるのかというところですよね。本当にいるんだったらお金をかけて開発やりましょうねということなんですけど、そこまではみたいなのだったらそれってなくてもどうにかなるっていうのは、これはある方からの受け売りですけどそういったことなのかなと思っていて、というところにご自身でもJSを試してみたこと。あとは、青竹のふしの青山さんとの出会いというところで気付かれたことだと。
前島:ええ、そうですね。
松井:青山さんを師と仰いでいらっしゃるそうですね。
前島:勝手に師匠と。良くしていただいて。
CUSTOMINEで連携サービスに対する考えが変わった
(13:57〜)
松井:病気になられたお子さんの状況だったりレポートとか、ご家族と共有しながらっていう事例だったと思いますけど、素敵なご事例というか素晴らしい時代だと思うんですが、そういった中で本質のほうに目を向けることがありながら、今回のカフェのテーマは連携サービスとかCUSTOMINEすごいですよっていうお話だったので、なんか矛盾してるなって思ったんですけど。
前島:さっき散々言っておいてっていう感じなんですけど、結局CUSTOMINEが出て、愛媛のkintoneカフェで企画のメンバーと相談していた時に1回ハンズオンもやったことあるし、今回も話出してみようかということで私が手を挙げさせていただいて、まだ気になっていながら使えていなかった、1回使ってみたいというのもあって手を挙げたんですけど、最初はCUSTOMINEってこんなもんですよという話にしようと思ってたんですけど、やっている時にふと思ったのが、奥は深いと思うんですけど開発を簡単に早くできるようになるということであれば、標準機能を使ってやっているのとほとんど変わらないなと。
松井:うん。
前島:プログラミングして開発するとなると時間もかかったりお金もかかると。そうするとkintoneの良さのスピード感が損なわれてしまうかもしれないと。本当に必要なことはやらないといけないと思うんですけど、意外にカスタマイズしようと思って出てくるやつの多くは、CUSTOMINEとかプラグインでできることが多いし、多いことがプラグインになっているんでしょうしというところで。そうするとどんどん使えるものは使っていって、開発してもらうのに比べたら遥かに安いし、すぐ使えて質も担保されているとなれば、使わない手はないなと。
松井:うんうんうん。
前島:むしろ、使わないことのほうがもしかしたら今のkintoneをより良くするチャンスを失っているんじゃないかなと思った時に、kintoneのユーザーで管理を担当してるものは標準機能でしっかりやるというのをまず大事にしながらも、プラグインがどんなものかとか、どうアップデートされているかとか、CUSTOMINEでより自分たち専用の改善が図れるようにという、この辺がkintone標準機能とセットで持っておかないといけないスキルなのでないかなと、その時は思ったんですよね。
松井:なるほど。
前島:安く早くできるというのがkintoneの良さだとすれば、プラグインもCUSTOMINEも同じだなと思ったので、そっちの話に変えたと。
松井:使っているうちに、こっちだねとなったわけですね。
前島:CUSTOMINEも使ってたら楽しかったですしね。慣れるのに1~2時間かかりましたけど、分かってくると面白いし。
松井:今の話ってアールスリーインスティテュートさん、CUSTOMINEの提供元の会社様でも私が取材した時にもお話しされていて、kintoneって標準機能の先の話になると途端に重くなると。プラグインがあるんですけどプラグインでできない領域、もしくはプラグインを使って変えたいなというところになってくると開発になって、イコールkintoneの変えやすいというのをなくしちゃう。ここをなんとか埋めたいなというところでCUSTOMINE を出されたという話だったので、もしかしたらアールスリーさんが泣いて喜ぶかもしれないですね。
標準機能と連携サービスの両輪で考えて行きたい
(18:46〜)
松井:これからは、どんどん連携サービスを入れていこうかなということなんですか。
前島:標準でやってて、割り切ってやっていたものの、こうだったらいいなと思ってきたことを、少しずつやっていくべきかなと。例えば、スケジュール管理的な機能でいくつかいいのが出てますし、CUSTOMINEもかゆいところに手が届くような1機能を追加できたりすると思うので、そんなのってまだまだうちのkintoneの中にあるし、うちのスタッフたちもkintoneに5年も経ったんでだいぶ慣れてはくれてるんですけど、無意識にここ微妙だなと思いながら我慢してくれてたとかあると思うので、そういったものをもう一度1から改善するチャンスかなというふうには考えています。
松井:そのお話ですと、なんでもかんでもどの業務にも入れたらいいというわけではなさそうなんですかね。
前島:標準機能で十分できてるやつとか、毎日使うアプリなのか、時々使うアプリなのかによってもカスタマイズしないといけないっていう必要性も変わってくると思うので、その辺優先順位をつけながらいけたらいいかなと思っています。
松井:前の話のところで、JavaScriptで変えれるっていうところは、最初見た目だったりというところに向いていて、業務改善の本質のほうに向いてなかったという話がありましたけど、今としては本質により向いているような部分で連携サービスとか、そういったところを入れていければなという理解でいいんですね。
前島:そうですね。相反するっぽいところなんですけど、両輪でいきたいかなと思っています。必ず必要なことは必要なので、それをいかに少しでも楽に使いやすくする、そこを追求しないといけないと思っています。
松井:最初にあえてライトコースというか、標準機能というところで利用されているところは、以前私がラジオで聞いた話ですと、スマイルアップの熊谷さんと話したときは、追加で入れるものには便利ツールのものが多いと。業務本質的には、改善の本質にはそれ本当にいるのっていう、あったら便利なんだけどなくてもいけるよねと。便利ツールばかり頼りにしてしまってると、足枷になるのもそうですし、そこばっかりに目が行っちゃって、さっきおっしゃってた本当にこの業務いるのとか、そういった改善ができないみたいな話を今思い出したので、そういった同じようなことなんだなと思います。
前島:そうですね。
松井:今ずっと運用されてきて残っている業務というのは、必要だからkintoneでやってると思うので、そこにプラスで連携サービスが加わればさらに改善できるんじゃないかなと思うので。さっき気になっているプラグインとしてはカレンダーとかそういったところですかね。
前島:あとはミドルウェアって言うんですかね。kintoneと他のSNSとかエクセルとかああいうものを繋ぐようなやつとか、そういうのも今気になっていて。例えば、うちの一部のスタッフは外からスマートフォンとかiPadとかで閲覧できるのは知ってるんですけど、kintoneたくさんアプリがあるので目的のところにいくまでに何クリックかかかると思うんですけど、ちょっとした連絡的なスペースとコメントみたいなやつはSNSに変えちゃって、そのデータがkintoneにも溜まっていきますというふうなこととか。
最近は表面的なものだけじゃなくて、そういうものも何かできないかなというのは、今情報を集めているところではあります。
kintoneへの改善要望
(23:32〜)
松井:色々お話伺えたんですけど、最後にkintoneに良くなってほしいなというか、こういった機能があったら嬉しいなというのがもしあれば教えて頂きたいんですが、何かありますか。
前島:以前と最近でちょっと違ってて、前はアクセスみたいにリレーショナルデータベース的な。
松井:ああ、データが入ったら、こっちにも入って。 前島:と、思ってた時期が長かったんですけど、今はそこまで思ってなくて。それこそCUSTOMINEとかで頑張ればできそうだし、そういうことよりも1つのドメインの中で、外から閲覧できるものを制限できないかとか。例えば、今社用携帯では結構見れるんですけど、個人携帯は見れないようにアクセス制限をしてるんですけど。
例えば、患者さんの情報とかは見れないですよとか。ただ、ちょっとした勤務の連絡とか、災害でも起こった時の連絡とか、そういう患者さんの個人情報じゃないようなことだけは、個人携帯というかスマホから見れますよみたいな。そんな切り分けとかができたりしたら面白いかなと思ったり。
松井:広がりますよね。
前島:特に私ども医療系なので、電子カルテとかも国が定めたガイドラインがあって情報管理とか閲覧とかパスワードのことにしても非常にルールがあるので、kintoneもそれに従わなくてもいいんですけどそれに近いような形でやっていたりするので、その反面みんながスマホでいつでも見れますっていうのができにくかったりするので。
松井:そうですね。切り分けのところが確保できれば、ガイドライン、国のほうに則って、もっと業務の幅を広げるというところですもんね。今だと、もう1個kintone契約してみたいな感じになっちゃいますもんね。
前島:はい。とかがあったりすると、面白いかなと。
松井:承知しました。ぜひフィードバックをさせて頂きますので、ありがとうございます。
前島:ありがとうございます。
松井:いろいろとお話を聞かせていただいて、ありがとうございました。内容としては、これからkintoneを使って頂く方にも参考になるというか、一度通ってきたからこそのご意見だと思いますので、参考にしていただければと思います。
そして、明日のkintone hiveも頑張ってください。
前島:頑張ります。
松井:本日のゲストは、ゆうの森の前島さんでした。ありがとうございました。



